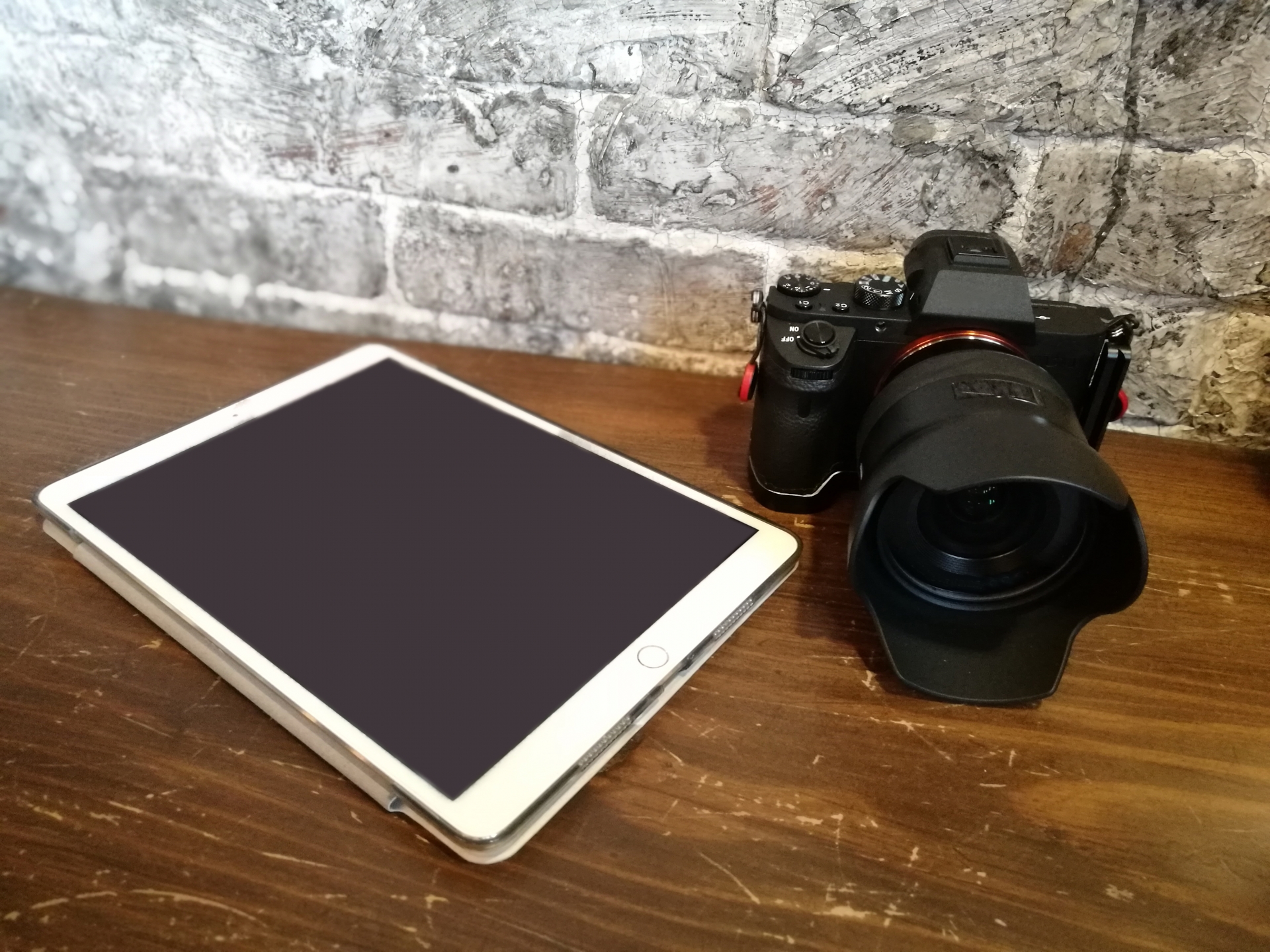結婚式に初めて出席することになった場合、ご祝儀をいつどうやって渡せばいいのかわからない人の方が多いでしょう。
一般的に、ご祝儀は袱紗に包んで結婚式で渡すということがマナーです。そのため、ご祝儀と一緒に袱紗を用意する必要があります。
今回は袱紗の包み方から結婚式での渡し方について詳しく説明します。大人のマナーとして正しく理解しましょう。
また、袱紗の種類と色についてもご紹介します。結婚式で渡す場合は、暖色系の袱紗を選ぶようにしましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

地鎮祭の服装にジーパンはOK?地鎮祭の服装と流れ・地鎮祭とは
地鎮祭を行う時、どんな服装で出席したら良いのかわからない人もいますよね。地鎮祭に何度も出席する経験が...
-
No Image
手動の灯油ポンプをうまく使うと、灯油を自動で入れることができます。この仕組みは一体どのようになってい...
-

喪中期間は結婚式の招待を断る?不幸があったときの結婚式マナー
自分の喪中期間に結婚式に招待された場合、結婚式に出席しても良いのか、マナーについて気になるものです。...
スポンサーリンク
袱紗を使ったご祝儀の包み方と結婚式での渡し方について正しく理解しましょう
結婚式に出席する時に、ご祝儀を包むのが一般的ですよね。
ご祝儀袋の書き方などについては、ご存知の方も多いですよね。しかし、ご祝儀の渡しについては、あまりご存じない方も多いようです。
ご祝儀袋をそのままバッグやポケットに入れている方も目にします。
残念ながら、それはスマートな大人とは言えませんね。
ご祝儀袋は袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包んで持参するのが正しいマナー
金封袱紗
最近よく使わるのは横型の封筒の様な形をしているタイプで、「金封袱紗」と呼ばれます。
袋部分にご祝儀袋を入れるだけという手軽さが、金封袱紗のメリットです。
金封袱紗は袋になっている部分を左にして、ご祝儀を入れてから右側を左へ向けて折りたたみます。
台付き袱紗・爪付き袱紗
他に、ただ「袱紗」と呼ばれる四角いハンカチのようなタイプと、袱紗に熨斗袋をのせる台のついた「台付き袱紗」があります。
また、これらに留め具がついている袱紗を「爪付き袱紗」と呼びます。
袱紗のたたむ順番を間違えると、不祝儀用の包み方になってしまい相手によっては縁起が悪いと不快にさせてしまうかもしれません。
爪がついている袱紗の場合は、爪が右に来るように広げます。爪がない場合には、ひし形になるように広げるだけでOKです。
- ご祝儀を中央よりやや左寄りに置きます。
- 左側を内側に折り、続いて上側、下側をたたみ、最後に右側をたたみます。
- 角がご祝儀袋のラインより飛び出ていますので、さらに折って完成です。
- 爪は留め糸にひっかけます。
袱紗の渡し方は種類によっても違います
ご祝儀は持ち運ぶ時には袱紗を使い包む時にも決まりごとがあります。
ですから、もちろん渡すときにもマナーがあります。
渡すマナーは使う袱紗によって少しずつ違います。
ですが基本的には、包んだときと逆の順でご祝儀を取り出して、袱紗の上に乗せてから、袱紗ごと180度回転させて相手の方へご祝儀を向けてから差し出します。
細かくご紹介しましょう。
金封袱紗の渡し方
- 袋部分を左になるようにして左手に置き、右側を開いて裏側へ折りたたみます。
- ご祝儀を取り出して袱紗の上に乗せてから、袱紗ごと相手の方へ向けてから差し出します。
台付き袱紗の渡し方
左手に袱紗を持ち、包んだ時の逆の順番で開いて、その度に裏側へ折ります。
- 右側を開いて裏側へ
- 下側を開いて裏側へ
- 上側を開いて裏側へ
- 最後に左側を開いて裏側へ折りたたみます。
この状態で袱紗ごと相手の方へ向けてから差し出します。
台のない袱紗の渡し方
最も難しく少し慣れが必要です。
包んだ時と逆の順で開くの一緒ですが、台付きとは違い四方すべてを開いてから、ご祝儀の下で包んだ時と同じ順でたたみ直します。
整えた袱紗の上にご祝儀を下ろして、袱紗ごと相手の方へ向けて差し出します。
台のない袱紗を使う場合には、当日スムーズにご祝儀を渡せるよに何度か練習しておくことをおすすめします。
袱紗の種類と結婚式に使う場合の色の選び方について
袱紗を用意しようとお店にいくと、たくさんの色が目に入ると思います。
無地のものが多いですが、中には柄が刺繍されているものもありますよね。
そこで重要になるのが袱紗選びです。
袱紗は熨斗袋を包む為のもの、慶事でも弔事でも使う
ですから、「色」がとても重要になるのです。
台付き袱紗の場合、台がリバーシブルになっているタイプは濃い紫色をしているはずですから、色の目安にするとよいでしょう。
また、袱紗の形は台付き、もしくは金封袱紗がおすすめです。
普通の袱紗や爪付き袱紗は、渡す時に手の上でたたみ直さなくてはいけず、その動作をスマートに行うためには、慣れが必要だからです。
袱紗の殆どは柄が無いのが一般的です。
柄ものをを選ぶ場合には、お祝いごとのモチーフである松竹梅や扇、鶴や亀などが向いています。
もし結婚式当日に袱紗を忘れてしまったら「ハンカチ」で代用しましょう
結婚式でご祝儀を渡すときには、袱紗に包むのが大人のマナーです。それは、新郎新婦に渡すときだけではなく、受付に渡す時でも同じです。
しかし、結婚式当日は新郎新婦だけではなくゲストもバタバタしてしまうものです。
特に女性の場合には、ドレスに化粧、ヘアアレンジに、ネイルなど、整えたい場所がたくさんですよね。
慌ただしく家を出ることになると、普段使い慣れていないので袱紗を忘れてしまうこともあるでしょう。
もしも袱紗を忘れてしまったときには、ハンカチで代用しましょう。
相手への礼を欠く行為です。
マナーの多くは相手を思いやる心遣いから生まれています。
袱紗は「贈り物である大切なご祝儀を汚さないように」という思いが発端ですから、袱紗がなければハンカチで包んで渡しましょう。
結婚式での袱紗の渡し方から芳名帳への記入まで、もう一度復習しましょう
初めて結婚式に出席するときには、手順がわからずにご祝儀の渡し方以外にも不安になることがありますよね。
ここまでご紹介してきたご祝儀を袱紗で包む方法や渡し方は、会場に到着してから結婚式が始まるまでの流れでいうと、意外と後半で役立つ知識です。
新郎新婦はもちろん、そのご家族や受付などのスタッフにも使います。
結婚式場に到着したら、一番始めに目指すのは「受付」
受付についたら、まずは先程の挨拶からはじめます。
そして「新婦(新郎)の友人の〇〇です。」という様に、新郎新婦どちら側のゲストなのかわかるように自己紹介します。
自己紹介が終わったら、袱紗を取り出して、先程の渡し方を参考にしてご祝儀を差し出します。
受付の方が受け取ったら、芳名帳への記入を促されると思いますので、そちらに名前や住所を記入します。
後ほど新郎新婦がお礼状などに使いますから、丁寧に記入しましょう。
受付が終わったら、時間までは自由です。
時間に遅れないように少し早めに席に付くようにしたいですね。
新郎新婦の新しい門出を祝って、大いに喜びを分かち合ってくださいね。