はじめて剣道の試合に出場する人は、どのように試合が進むのか、一連の流れについて知りたくなることだと思います。
練習中にしっかりとチェックしていても、緊張から作法を間違えてしまうかもしれないと、不安な気持ちになっている人もいるのではないでしょうか。
剣道は「礼に始まり礼に終わる」と言われる武道の一つです。一連の試合の流れや作法をチェックして、試合でミスをしないようにしましょう。
ここでは、剣道の試合の流れや「礼」についてお伝えします。剣道の作法を学び、試合当日の緊張を少しでもほぐしてください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
No Image
結婚式はその人にとって、特別に大事な日ですから、出来るだけ祝福してあげたいですよね。しかし、人に...
-

バレエのコンクールに出場する時に先生に渡すお礼の相場と考え方
お金がとにかく掛かることで有名なバレエ。普段の月謝や衣装代だけでもお金が掛かる上、コンクール出場...
-

明日ある面接に緊張している人へ。緊張をほぐす方法を紹介します
明日の面接では緊張しすぎて上手くしゃべることができないのでは・・失敗してしまったらどうしよう・・と不...
-

墓参りで供えた花の片付けはどうする?素朴な疑問にお答えします
墓参りの時にはお花を供えますが、その後の片付けのことまで考えたことはありますか?お供え物は持ち帰...
-

榊や神棚の手入れ方法・手入れする時のポイントや注意点はコレ!
自宅や会社にがある人や、これから神棚を設置するという人の中には、神棚や榊のお手入れ方法がよくわからな...
-
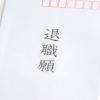
離職票の退職理由が体調不良の場合に手続きや知っておきたいこと
離職票の退職理由が体調不良の場合には、失業給付のことなど手続きを確認しておく必要があります。...
スポンサーリンク
剣道の試合開始時の流れについて
相手へ失礼の無いように、剣道の作法は身につけておきたいものですよね。
剣道の試合開始時の一連の流れをご説明していきます。
試合開始時の流れ
- 相手に向かう
- お互いにしっかりと礼をする
- 3歩前に出る
- 構えながら蹲踞をして剣先を交える
- 蹲踞の状態から主審の「はじめ」の合図でお互いに立ち上がって試合開始
コートに入る前に礼をする人もいますが、これは間違いなので相手と向かい合ってからしっかりと礼をしましょう。
相手に向かうとき、3歩で蹲踞ができる場所にいなければ4歩、5歩と前に出なくてはいけなくなるので気をつけましょう。
礼は15度頭を下げましょう。
蹲踞とは、体を丸くしてしゃがむことを言います。
なぜ蹲踞をするのかというと、相手を敬い感謝しているという礼の心を表すためです。
どんなときでも、相手への敬いの気持ちを忘れてはいけないということですね。
剣道の試合終了時の流れについて
上記では試合開始時の流れについてご説明しましたが、今回は試合終了時の流れについてご説明していきます。
試合終了時にも作法を忘れてはいけません。
試合終了時の流れ
- 勝敗が決まったら試合開始の際に蹲踞した位置に戻る
- 蹲踞をし、竹刀を納める
- 収めたら立ち上がって後ろに下る
- お互いに礼をして退場する
この時の礼も15度頭を下げましょう。
試合が決勝戦の場合、向かい合ってお互いに礼をした後正面に向かってもう一度礼をします。
また、大会が開催され、2日以上に渡る場合は1日の最後の試合終了のときも向き合って礼をした後正面に向かって礼をします。
試合開始時や終了時の作法ができていないと、指導者の指導力や自分の強さのレベルが低く見られてしまうことがあるので、作法はしっかりとしておきたいものですね。
剣道の試合での入場・整列・正面への礼について
試合開始時や終了時だけではなく、試合での入場・整列・正面への礼についてもルールがあります。
入場・整列・正面への礼のルールをしっかりと覚えて試合に挑みましょう。
- 入場
入場の際は選手席に整列して、監督の指示で正面に礼をしてから着座します。 - 整列
団体試合の場合、先鋒、次鋒は剣道具を着けて竹刀を持ち、立礼の位置に整列して主審の「礼」の号令により相互の礼を行います。
引き続き次の試合が行われる場合、試合場内に2チーム1列で並びます。 - 正面への礼
試合者は第1試合の開始時や決勝戦の開始時と終了時に正面への礼を行います。
また、試合が2日以上に渡る場合は第1試合の開始時と最後の試合の終了時や、決勝戦の開始時と終了時にも正面への礼を行います。
正面への礼は立礼の位置で行います。
以上剣道の試合での入場・整列・正面への礼のルールについて説明しました。
慣れるまではルールが曖昧になってしまうかと思いますが、しっかりと体にルールを覚えさせましょう。
剣道の試合の流れは「礼に始まり礼に終わる」
剣道は「礼に始まり礼に終わる」と上記でご説明しました。
この言葉通り、剣道はまず初めにお互いの礼を交わすことから始まります。
このときの礼は臨戦態勢という意味合いなので15度の浅い礼をし、深くまではしません。
相手と視線をしっかり合わせながら礼をします。
このとき、相手から視線をそらさないようにしましょう。
剣道という武道において、礼はとても大切なものなのです。
試合前の浅い礼は臨戦態勢という意味合いがありますが、試合終了時や正面への礼をするときはかならず相手を敬い、感謝の気持ちを持って礼をしましょう。
このような作法も慣れてしまえば身につくものですが、流れ作業にならずにひとつひとつの動作に意味合いがあるということを感じ、気を引き締めて行いましょう。
剣道の試合で大切な「礼」
剣道には立ってする「立礼」と座ってする「座礼」があります。
この立礼と座礼はどんな礼なのでしょうか。
立礼
立礼とはその言葉通り立って礼をします。
背筋を真っ直ぐに伸ばしたまま腰をゆっくりと曲げて行います。
道場への出入りや稽古相手、試合相手などへは15度ほど腰を曲げて礼をします。
先生などの目上の方には45度腰を曲げて礼をします。
座礼
正座の状態から両手両肘を付き、礼をします。
このときもなるべく背筋を伸ばしたままゆっくり両手、両肘を付いて行います。
手は親指と人差し指の指先をつけて三角形を作るように揃えましょう。
三角形の中に鼻を入れるような気持ちで頭を下げていくと綺麗に礼ができます。
以上立礼と座礼についてご紹介しました。
いかがでしたか?
相互の礼であれば竹刀を左手に持っていても良いですが、目上の方に対しての礼のときは竹刀を右手に持ち替えて行いましょう。
左手に持ちながら礼をするのは無礼とされているので気をつけましょう。













