普段は箸を使う日本人にとって、洋食のテーブルマナーはちょっと苦手という方が多いのではないでしょうか。
洋食のフルコースなどになると、魚や肉料理も、フォークを使い食べなければいけません。
そこで、洋食で魚料理を食べる時の、上手な食べ方のマナーをご紹介します。魚料理には骨がありますが、手順を覚えておけばきれいに食べることができます。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

スノーボード初心者への教え方!楽しく安全に滑る基本のステップ
スノーボードを初めて滑るという方には、何から教えれば良いのでしょうか?まず、初心者は転倒が多くな...
-
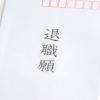
離職票の退職理由が体調不良の場合に手続きや知っておきたいこと
離職票の退職理由が体調不良の場合には、失業給付のことなど手続きを確認しておく必要があります。...
-

卓球の練習方法・初心者の中学生の練習と一人でもできる練習方法
中学生になってから卓球を始めた人の中には、周囲と比べてなかなか自分のテクニックが上達せずに悩んでいる...
-

上司との喧嘩【仲直り】は部下から言うもの。大人の階段を上ろう
上司と喧嘩になってしまった!仕事を辞める選択肢も頭をよぎるも、そんな子供みたいなことはすぐにはで...
-

年賀状のコメントなしは失礼になるのかどうか【年賀状のマナー】
毎年の年賀状はいつも年末ギリギリになって準備を始めるという方も多いと思います。そこで気になるのが...
スポンサーリンク
洋食で魚料理を上手に食べるためのマナー
20代半ばになると出席する結婚式や、友人彼氏とお洒落な洋食レストランに行く機会も増えてきますね。
食事をする時、主に箸を使う私達はフォークやナイフを使った食べ方に慣れていません。いざと言う時に恥ずかしい思いをしないためにも、ここで洋食の食べ方のマナーを覚えておきましょう。
洋食の魚料理の上手な食べ方とマナー
魚の皮
洋食の魚の皮は基本的に食べられます。
しかし皮が苦手だったり厚くて食べれないな場合には最初にフォークとナイフを使って剥がします。
添え付けの野菜
魚と一緒に食べても、野菜のみで食べてもOK。
好みに合わせて食べましょう。
ソースにつけながら食べる
ソースがある場合は、口に入れる前にソースを少しずつつけて食べます。
食べ終わりの皿がソースで汚くならないように食べ進めていくのが洋食のマナーのポイントでもあります。
魚を裏返さない
魚の食べ方をいまいちわかっていない人は魚を裏返して、自分なりに食べやすいように食べてしまうこともあるでしょう。
洋食では魚は裏返さないのがマナーです。
お皿に盛り付けられているまま、左端から食べましょう。
慣れない洋食のマナーを意識して食事をするのは大変疲れますよね。
しかし、若いうちに洋食の魚の食べ方を覚えておくと便利ですよ。
年齢と共に洋食のマナーが身についてきます。
そうすると、洋食をもっと堪能することができるでしょう。
魚などの温かい料理は冷めないうちに食べるのが洋食のマナー
洋食はコースででてくることが多いです。
コース料理を食べ慣れない私達は、どんな食べ方が正解かわからず周りを見て見よう見まねで食べていたりしませんか。
私もそんな時がありました。
失礼ない食べ方をしなければという思いで、せっかくの料理も堪能できなかった記憶が何度かあります。
まず、コース料理の印象はどんなものをお持ちですか。
私は「量が少ない」「美味しいからもっと食べたい」です。
量が少ないと感じてもそれがどうしてなのか理由を考える人は少ないでしょう。
しかし、それはコースならではの配慮が隠されています。
なぜなら、温かいものは温かいうちに食べきる、冷たいものは冷たいうちに食べきる、というコースを提供する店側のサービスの意味が込められています。
出された料理に品質が落ちないうちに食べきる、これがそのサービスの正解です。
つい、話に夢中になって食べるのが遅くなってしまうことがあるでしょうが、お店側もタイミングを見計らって一品一品料理を用意しています。
お話しながらでも食べ進めてあげるとお店側もスムーズに料理を提供することができます。
とっておきの日に食べることが多い洋食です。
食べ方のマナーを覚えて安心してその場と料理を楽しめるようになりましょう。
洋食の魚料理に使うフィッシュスプーンの正しい使い方
洋食には魚も多くでてきます。
魚の種類によって見が崩れやすいものがあります。
そんな魚を食べるためのスプーンが用意されています。
そのスプーンで食べやすい大きさ(一口サイズ)に切って食べましょう。
スプーンですくいづらい時は左手にフォークを持ってすくう時に添えると食べやすくなり、またよりスマートな食べ方になります。
食事中にフィッシュスプーンなどカトラリー(スプーン、フォーク、ナイフ)を落としてしまった場合には、その音で店員さんが気づいてくれます。
店員さんが対応してくれるまでそのまま待ちましょう。
洋食では自分で拾うことはマナー違反です。
なぜなら、「他人の足元を除く」とみなされてしまうそうです。
スプーンなどの扱い方にはこんなマナーがあるとは知らない方も多いでしょう。
洋食のコースではくれぐれも気をつけてくださいね。
女性が気を付けたい口元のマナー
洋食を食べる時の女性のマナー
お洒落な場所で洋食のコースを食べるということもあり、服装やお化粧にいつもより気を使う女性も多いでしょう。
しかし、洋食を食べるマナーには女性の口紅にも要注意しなけれないけません。
グラスやカトラリーに口紅がべっとりとついてしまうのはあまり良くありません。
食事前にトイレで口紅を軽く落として置くと良いでしょう。
もし、口紅がついてしまったらさりげなく親指で拭くとよいでしょう。
食事中に口が汚れたら、子供のように舌で舐めるのは絶対に避けてくださいね。
膝に置くナプキンで口を拭きます。
ナプキンを元に戻す時は汚れが見えないようにしてください。
日々無意識にやっていることは、どんなに気をつけていてもでてしまうことがあります。洋食に限らず食べ方のマナーは和食でも共通する部分が多いです。
普段から食事のマナーを意識することが大切です。
フォークとナイフの置き方もスマートに
洋食を食べ終えたらフォークやナイフをどうしてますか。
私達は普段食事を食べ終えたら箸をお皿などの上に揃えて置くのが普通ですよね。
洋食でも同じくフォークやナイフを揃えて置くことが食べ終わったという合図になります。
洋食では食べ始める時、両端にフォークやナイフが並べられてますが、食べ終わりは右側に揃えて置くことを覚えておきましょう。
また、食事中のフォークとナイフの置き場所に困ってしまうこともあるででしょう。
そんな時はフォークやナイフを皿の上にハの字に自然に置いておくと食事中という合図になります。
私も友達の結婚式の会場で洋食コースを食べることがあります。
使い慣れないフォークやナイフ、お洒落な料理にあたふた周りを気にしながら食べてしまうことが何度もありました。
美味しいはずの料理も、マナーが正しいのか気になって堪能しきれないこともよくありましたよ。
普段食べられない料理をもっと堪能したい、という思いからネットで洋食のマナーを調べ、また結婚式に行く回数が多くなるに連れて、少しずつ知識をつけることができました。
あなたの年齢ではこれから結婚式に招待されることも多くなるでしょう。
今のうちに洋食のマナーの知識をつけることでいざという時困ることがありませんね。
結婚式の会場だけではなく、彼氏のフレンチコースの急なお誘いにも恥ずかしい思いをすることがありませんね。
楽しく洋食を堪能できるよう洋食のマナーを覚えておくことをオススメします。














