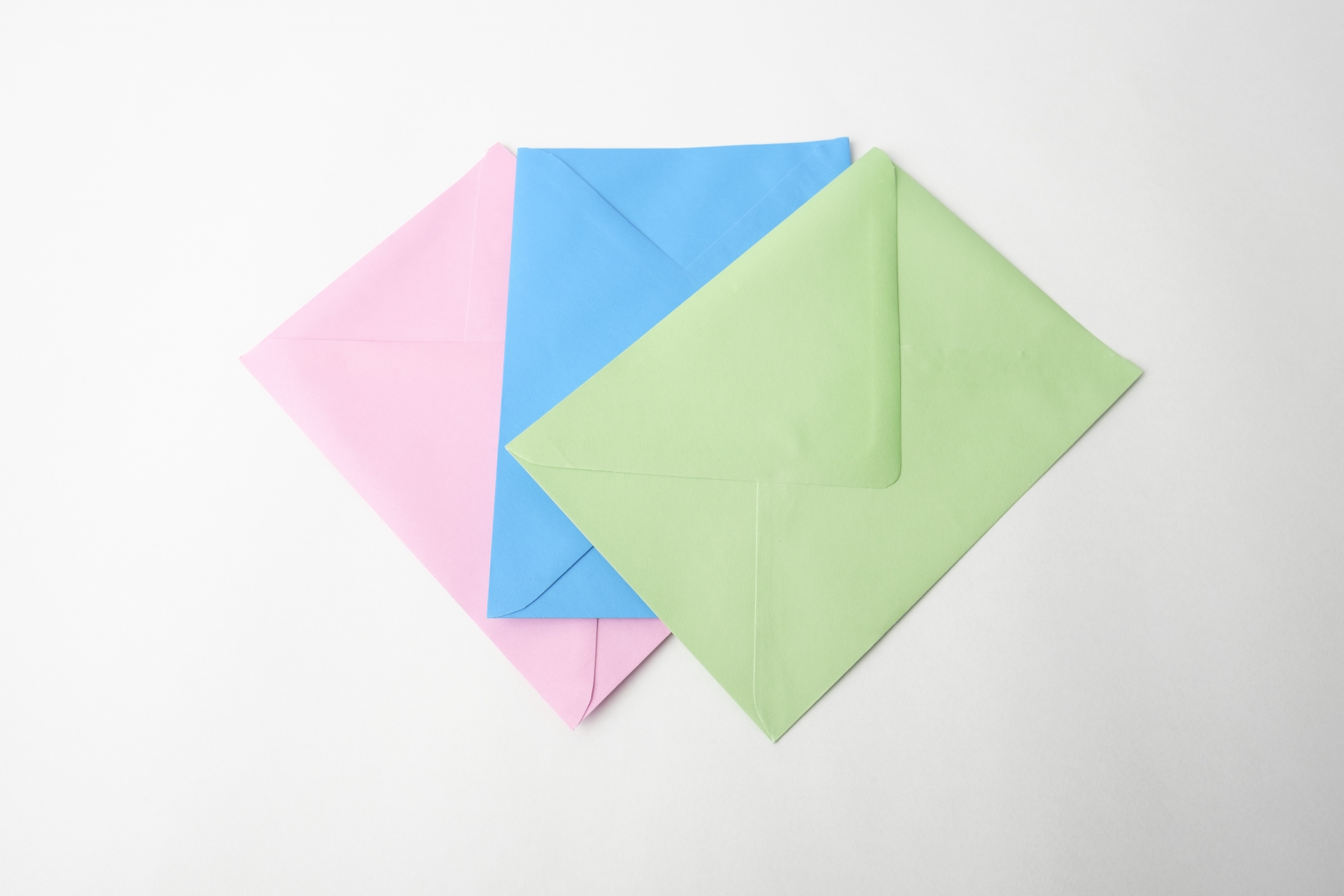ゴミ出しのルールを守らない住民に対して、ルールを明記した文書を作成することがあります。
文書には「ルールを守りましょう」といった内容の文を明記すると思いますが、その文書だけでは効果が薄いかもしれません。
ゴミ出しルールの文書を作成する時にはポイントがあります。
効果的な文書の作り方についてご紹介しますので是非参考にしてください。
それでもルールを守らない住民に対しては毅然とした態度をみせることが大切です。
まずは文書で忠告をしましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

内定の報告を先生にしたい!メールや手紙で報告する場合の注意点
苦労した就活でようやく内定がもらえたら、これまでお世話になった先生へ報告したいですよね。でも...
スポンサーリンク
ゴミ出しのルールについて文書を作成する時のポイント
本当に文書を見てほしいのは、このような人ではなく、ゴミ出しのルールを守らない人達なのですが、「ルールを守りましょう」といった抽象的な書き方では、その人達には何も伝わらないというのが実際の所…。
ルールを守らない悪質な住民に、ゴミ出しのルールを書いた張り紙にしっかり目を通してもらうためのポイント
文書作成のポイント
- 一番見てもらいたい部分を強調する
文書をパソコンで作成する場合にも、手書きで作成する場合にも、有効なのは、「文字の大きさを変える」「文字の色を変える」「文字のフォントを変える」「アンダーラインを引く」などの方法で強調することです。 - 肯定文で書く
「~しないでください」のような否定的な書き方は、おすすめしません。
「生ゴミが袋の外から見えるように入れないで下さい。」と書かれるよりは、「生ゴミは新聞紙などで包んでから、見えないようにして入れて下さい。」と言い換えたほうがすんなりと読めませんか?
「ゴミを手前から入れないで下さい。」よりも「ゴミは奥から順番に入れて下さい。」の方が、何をすべきかが明確になり、ルールが簡潔に伝わりますよね。ルールが守れない人の中には、正しい方法がわからないがために無意識にルールを破ってしまっているということがあります。すべきことを端的に伝えることで、「そういうことか!」と納得できる人が増えるはずです。
ゴミ出しについてのルールを述べた文書に不法投棄されたゴミの写真を添付するのも効果的
その人が仕事から帰ってくるのは、ゴミの回収が終わった夕方を過ぎてからなので、ゴミの回収は終わっているし、路上に散らかったゴミは私が掃除したため、片付いています。
まさか自分のゴミが荒らされているとは知らないでしょうし、万が一わかっていたとしても、帰ってくる頃には片付いているので、ゴミの出し方は変わりませんよね。
私の住んでいるアパートは小さなアパートなので、ゴミ出しの文書が張り出されることはありませんが、大きな集合住宅などの場合には、ゴミの不法投棄や、分別されない混合ゴミの放置などがあると聞きます。
そのような場所で管理を任されている人にとっては、ルールを守らないゴミ出しをする人たちの問題は本当に深刻ですよね。
先程紹介したゴミ出しのルールを記載した文章作成のポイントに加えておすすめしたいのが、「写真の添付」です。
ルールを守らない人たちは、自分が捨てたゴミのせいでどのような被害があるのかを実感していない人が多いため、写真を添付することで「自分の出したゴミだ」というのを自覚してもらう必要があります。
燃えるゴミや不燃ごみであれば、中身があまり変わらないので誰のものか写真では区別が難しいかもしれませんが、「粗大ごみ」や「不法投棄されたゴミ」であれば、当の本人にもしっかり伝わるでしょう。
「自分の出したゴミだ!」「悪いことをしてしまったな」と思ってくれさえすれば、同じようなことは起こさなくなるはずです。
「ゴミ出しのルールを守らない場合はゴミを点検して調査する」といった内容を文書に記載しておくのもおすすめ
しっかりと文章で忠告をしているにも関わらず、ゴミ出しのルールが改善されないというのは残念なことですが、多くの方が経験していることではないかと思います。
ゴミ出しのルールを記載した文章の書き方を工夫しても、写真を添付してみても、状況が悪化するばかりだという場合には、ゴミを点検してルール違反をしている住人を突き止めるしか方法がありませんね。
「ゴミの点検」は、ゴミから得た個人情報を第三者に言いふらしたり、管理人でもない一個人が他の住人のゴミを開封したた場合にはプライバシーの侵害で訴えられてしまうことがあるかもしれませんが、ゴミの管理、住環境の維持を目的としたものであれば、「管理人」や「管理会社」がゴミを開封して点検することは違法にはなりません。
「ゴミ出しのルールを守らない場合には、ゴミを点検させていただきます」と一言書き加えておきましょう。
文書を出してもゴミ出しのルールを守らない住民がいた場合の対処法
きちんとしたルールに則って、文書で警告をし、ゴミ出しのルールを住民に周知したのにも関わらず、ゴミ出しのルールを守ってくれない住民がいたとします。
ゴミの点検によって、ルールを守らない住民がはっきりとしている場合には、毅然とした態度で、ルールを守るように直接伝えていきましょう。
ルールを守らない住民にのみ文章を送るのも良いでしょうし、ゴミ出しのスケジュールや、ルールをまとめた文章をお渡しするのも効果的です。
誰がルール違反をしているかは、映像にしっかりと残るので、アパートの出入り口やゴミステーション付近に設置をして、犯人を特定しましょう。
ゴミ出しを守らない場合は文書を使ってまず知らせ、それでも効果が薄いのであればカギの取り付けや監視カメラを導入するのがおすすめ
これまで紹介してきたように、ゴミ出しのルールを守らない人への対応は、順を追って行っていく必要があります。
最後におさらいしていきましょう。
ゴミ出しのルールを守ってもらうために
- ゴミ出しのルールを文章にして張り出し、住民にも配布する(文字の強調、肯定文、写真の添付などのポイントも忘れずに!)
- 必要であれば、ゴミの点検をすることを周知し、ルールを守らない住民を特定する
- ゴミ出しのルールが改善されない場合には、監視カメラを導入する
- 住民以外の人がゴミを捨てている場合には、ゴミ箱に鍵を付ける
4の方法ははじめて紹介しましたが、中には、近所からゴミを持ち込んで、アパートのゴミステーションにゴミを不法投棄する方もいます。