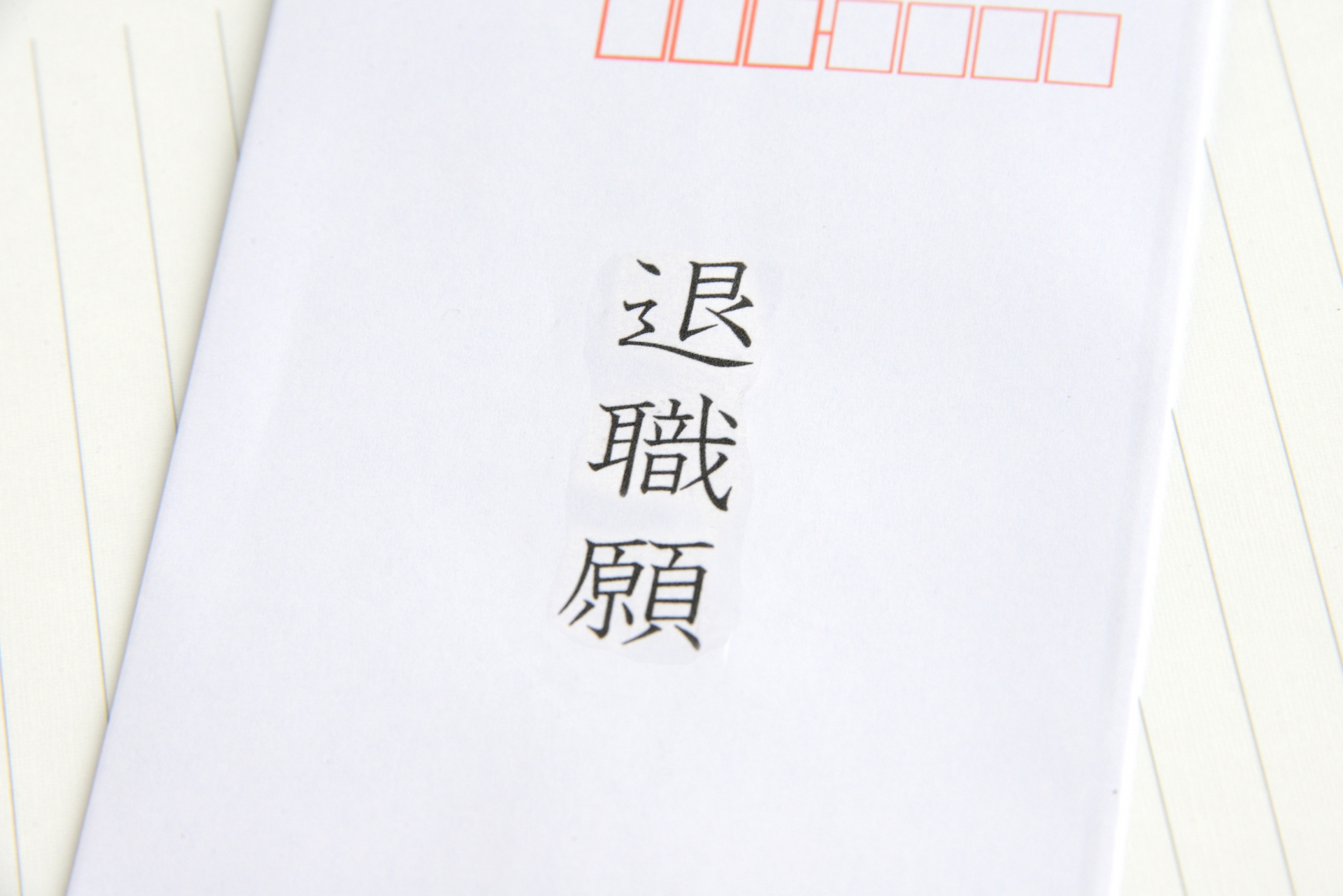電話での相手の会社の呼び方は書面の場合とは違ってきます。これから社会人として働くなら、取引先の呼び方には気をつけなければなりません。相手に失礼がないように呼び方の使い分けをすることがビジネスマナーとして大切になります。
そこで、気をつけたいビジネスマナーについて、電話での相手の会社の呼び方や書類やメールでの相手の会社の呼び方、電話か書面かで相手の会社の呼び方を使い分けをすること、自分の会社を表す言葉や企業以外の取引先への正しい呼び方などお伝えしていきましょう。
これで、これから取引先に電話をかけるときやメールを送るときでも呼び方に気をつけることができます。ぜひきちんとしたビジネスマナーを身に付けましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

ラーメンの食べ方のマナー!デートでラーメンを食べる時のマナー
好きな人や彼氏とのデートでラーメンを食べることもありますよね!その時、気をつけたほうが良い食べ方のマ...
-

ゴールドの結婚指輪の着用は葬式でOK?NGとされるデザインは
ゴールドの結婚指輪は肌なじみが良いと人気です。しかしその一方で葬式などにつけていっても大丈夫?と心配...
-

勉強がストレスになったら泣くことで発散!勉強ストレス解消方法
一生懸命勉強をしていると、どんどんストレスが溜まってしまうものです。勉強することが泣くほど嫌に思える...
-

運動は食前にする?それとも食後?運動を行うタイミングについて
運動するなら、効果を最大限にする方法で行いたいですよね。運動って、食前にするべきなのでしょう...
スポンサーリンク
電話での相手の会社の呼び方は御社です
新社会人の皆さん。内定を貰った会社から電話の受け答えについて、研修もあったかと思いますが、それでも「電話応対、苦手」と心の中で感じている人、いますよね。
電話で話す言葉も、謙譲語や尊敬語など、頭で考えながら話さなくてはいけません。他の会社で働いている方を電話で呼び出す時、「御社」という言葉を使います。
つまり、実際に電話で呼び出して貰う時は、「御社のOO様お手すきでしょうか?」など、相手の会社名は、「御社」という呼び方をします。
慣れて来たら、仕事上、取り引きのある会社に電話をする時、「御社」という言葉を使用することにも何も抵抗が無く会話がはずみます。初めは学生時代には中々使用しない言葉なので、口が上手く回らないかも知れませんね。
相手の会社に電話をする時は、御社だという事、覚えて電話を掛けるようにしましょう。多分、面接の時にも御社という言葉を使用したと思うので、それ程違和感は無いと思いますが。
書類やメールでの相手の会社の呼び方は電話の場合と違う
会社で書類を作成する機会も多くあります。社会人になると、パソコンを使う機会も増えます。そうすると、自分の会社を示す言葉が何であり、それが会話の時はどうなり、文章の様な書面にすると、変わることに気づきます。なんだかルールの様で堅苦しいと思いますが、それも社会人として、なれる必要があります。
呼び方の違い
会社で、話す場合は、「御社」という言葉を使います。御社というのが、話す際には適切な言葉になります。ですが、それが、相手の会社へ送る書くものになると、言葉が変わります。「貴社」なんて聞いてみたら社会人らしい言葉に変わります。
今、就活をする際に、エントリーシートが頻繁に利用されています。就活をしている方は注意して頂きたいのですが、その様に一見、パソコンを利用してでも「入力する」という動作になると、その時も、エントリーシートに入力しなくてはいけない言葉は「貴社」になります。恐らく面接官もその知識があるかどうか試していると思います。ですので、就職活動をする際、また内定を貰った会社で働く際、言葉の表現には十分気をつけて下さい。
漢字も似ているので見分けがつき難いかも知れませんね。話す時は、御社、書く時は貴社という風に使い分けして覚えて行くと、仕事上でもミスが出ないと思います。
新人社員だと間違えても多めに見てくれる事もあるとは思います。ですが、「一般常識でしょ」と怒られるかも知れないので、頭にはしっかりと入れて置きましょう。
電話か書面かで相手の会社の呼び方を使い分けしましょう
就職活動をしている時、本を購入すると、「御社」と「貴社」の使い分けに付いて念入りに書かれているページもあると思います。注意事項か何かで書かれていると思います。
ついつい間違えてしまいそうな表現ですよね?どうやって違いを覚えたら良いんだろう。
簡単に言うと、話している時は、「御社」という言葉を使用し、何か「書く」という動作が伴う時は、「貴社」という表記になります。ですので、あなたがどういった動作をするかでどちらを使用するか、変わって来ます。
これから面接を受けるのでしたら、「話す」という動作になるので、使う言葉は「御社」になります。ですが、既に働いていて、ビジネスの紙でタイピングするのであれば、それは「貴社」になります。そう考えると、ミスの回数も減って来ると思います。
この二つの使い分けがいつまでも出来ないと、社会人として失格だという評価を周りから受けてしまうと思います。なるべく、間違わない様に努力しましょう。
自分の会社を表す言葉にも気をつけましょう
相手の会社の方と話す時に、今度は自分の会社の事を示す適切な表現、あなたは知っていますか?
それは、「弊社」になります。自分の会社ではない、別の企業の方と話し、かつ、自分の会社の事を会話で話す時は、「弊社」という表現を使います。
ん?それじゃ、「当社」という表現を聞いた事があるけれど、弊社と当社では何が違うの?と疑問に持たれるかも知れませんね?
当社と弊社の呼び方の違い
あなたが誰と話しているのか、という事がポイントになって来ます。もし、あなたが自分の会社の人と話すのであれば、「当社」という言葉になり、自分の会社以外の人と会話するのであれば、「弊社」が適切な言葉遣いになります。
これも、つい口がすべって、どっちがどっちだか理解らなくなる事もありますよね。話す相手が自分の会社の人であれば、当社、別の会社の人であれば、弊社だという事を覚えて置きましょう。
企業以外の取引先へも正しい呼び方に変えるのがマナーです
会社に勤務している間、様々な会社の方とコミュニケーションを取ります。中には、コミュニケーションをとる方の中で、「会社」ではなく、学校や銀行と取り引きがある事もあります。
そんな場合、会社ではない取引先を呼ぶ名称は、少し難しくなって来ます。相手が学校であれば、「御校」になり、銀行になれば、「御行」になります。
基本的には、「御」という漢字が付きますが、中々使い分けが難しくなります。会社ではない取引先と話す機会が多いと、違った言葉遣いにも慣れて来るかも知れませんが、そうでもないと、中々企業以外の会社の呼び方は覚えるのは難しいと思います。
とりあえずは、上記に紹介した、学校と銀行の呼び名を覚えて行きましょう。それだけでも、「マナーが出来ているね」と周囲から中々の評価を得ることが出来ます。
周りの先輩に前もって聞いて見るのも良いと思います。先輩とのコミュニケーションも取りやすくなります。
電話で相手の会社を呼ぶ時に、どんな言葉が適切になるのか、上記の記事で説明して来ました。参考にはなりましたか?書面ではどうなるのか、相手が銀行など、会社以外の組織であるとどういった表現が正しいかについても説明してきました。出来るだけ、会社での言葉の表現のミスが減るよう、助けになれば幸いです。