相撲を見ているとお相撲さんの他にも、行司や行司の掛け声に注目が行きます。
行司の掛け声には意味があり、耳馴染みのある「はっけいよい、のこった」にも、何通りかの説が存在します。
またその他にも行司の掛け声はいくつかあり、意味や特徴がわかると、相撲をより楽しく見ることができます。
お相撲さんだけではなく、行司さんのファンにもなってしまうかも知れませんね。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

御祝儀を連名で包むときの表書き・友達と連名で包むときの書き方
友達同士で御祝儀を包むことになった時、連名で包む場合は、御祝儀袋の表書きにどのように名前を記載すれば...
-

品出しバイトの志望動機のコツ!即採用に繋がるポイントの考え方
品出しのバイトの志望動機では、自分がどうして品出しのバイトに応募したのかという理由やきっかけを答えな...
-

野球のドラフトの仕組みについて気になるルールを解りやすく解説
野球のドラフト会議の仕組みについて、野球を観るのは好きだけどドラフト会議の仕組みやルールまではよく解...
-

化粧をしない女性は社会人としてマナー違反?化粧に対する考え方
「化粧をしない女性は社会人としてマナー違反だ」という議論が世の中を騒がせていますが、女性が化粧をしな...
-

結婚式に履く靴の素材にスエードはOK?結婚式の靴マナーを解説
結婚式にゲストとして出席するときに考えるのが、洋服や靴などのマナーについてです。結婚式でマナー違...
-
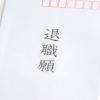
離職票の退職理由が体調不良の場合に手続きや知っておきたいこと
離職票の退職理由が体調不良の場合には、失業給付のことなど手続きを確認しておく必要があります。...
スポンサーリンク
相撲の行司がいう「はっけいよい、のこった」の掛け声の意味について
相撲の行司がいう「はっけいよい、のこった」の掛け声の意味について考えたことがありますか?
実は意外と深い意味がありそうです。
それでは「はっけいよい、のこった」という言葉について学んで行きましょう。
まず、「はっけよい」という言葉についてですが、実は「はっけよい」という言葉の意味はハッキリとしていません。
というのも、語源の説が3つあるからです。
その3つの説をご紹介します。
- 八卦良い
「はっけよい」の語源のひとつとされているものに「八卦良い」というものがあります。
八卦とは中国における占いの用語で、8つの自然に起こる現象を表しています。
ですので、言い換えると「(占いにおいて)良いタイミングになったよ。」といったところでしょうか。 - 早く競え
「『はっけよい』と『はやくきそえ』じゃ全然違うでしょ」と思った人もいると思いますが、今と昔とでは言葉使いが違います。
昔は「早く」を「はや」、「競え」を「きほへ」と言っていたそうです。
そして、それを早く言うなどして転じたのが「はっけよい」と言われています。 - 発気揚々
3つ目の説には「発気揚々(はっきようよう」から来ているというものもあります。
発気揚々とは「気力が極限まで高まっている」といった意味があり、その言葉が転じて「はっけよい」になったとも言われています。
全力で体をぶつけ合って戦う相撲にはピッタリの言葉ですね。
ちなみに「残った」の意味ですが、相撲は土俵に手や背中などをつく以外に、土俵から出ることでも負けが決まります。
そうならないように「土俵に残れ」という意味を込めて「残った」と言われていると考えられます。
相撲の行司の掛け声は他にもいろいろとあります
相撲の行司の掛け声は「はっけよい、のこった」だけではありません。
その前に「見合って、見合って」などのセリフも言っていますよね。
取り組みの際のの行司の掛け声は他にもいろいろとあります。
そのいくつかをご紹介します。
- 「見合って」
- 「時間です」
- 「構えて」
- 「待ったなし」
- 「手をついて」
などがあります。
これらの言葉には特に決まりがなく、その時に立ち会う行司の人が決めているそうです。
ちなみに、取組の際のお相撲さん同士の呼吸が合わないと感じた時は「まった」など、仕切り直しをさせるために声をかけます。
相撲の行司の掛け声、しこ名の呼び上げにも種類が存在
相撲の行司の掛け声の中には、しこ名の呼び上げにも種類が存在するってご存知でしたか?
お相撲さんが土俵に上がる時に行司が「ひが~し~、〇〇海~、に~し~、××山」とお決まりのセリフを言います。
これを「呼び上げ」と言います。
すべてこの言い方にしていると思われますが、実はこれが小結以上の「三役」と呼ばれるお相撲さんの場合ですと、「かたや〇〇海~、〇〇海~、こなた××山~、××山~」のように、「東と西」ではなく、「かたやとこなた」変わり、また四股名も二回呼び上げるのです。
ちなみに一回四股名を呼び上げることを「一声(いっせい)」と言い、二回四股名を呼び上げることを「二声(にせい)」と言います。
また、十両最後の取組の時も二声で呼び上げます。
相撲の行司の掛け声「構えて」には、行事それぞれの特徴が!
相撲の行司の掛け声「構えて」には、行司それぞれの特徴が出るそうです。
相撲を行う時に大切なのは、勝敗をしっかり見定めるのと同時に「時間を守る」ということも大切です。
というのも、相撲の取組はテレビ中継されますので、その番組の時間内に出来るだけ終わらせるようにしないといけないのです。
早すぎてもダメですし、遅すぎてもダメなのです。
その時間を見ながら「取組の時間が来ましたよ」といったことを言葉でお知らせするのです。
主に「構えて」、「見合って」といった言葉をよく耳にすると思いますが、中には「睨み合って」、「油断なく」といった言葉もあるそうです。
他にもその日の最後の取組の際に呼び上げた後に「この相撲一番にて本日の打ち止め」などと、その日の取組が最後であることも伝えます。
相撲は行司の掛け声以外に場内放送にも耳を傾けてみてください
相撲の取組の際に言葉を発するのは行司だけではありません。
相撲は行司の掛け声以外に場内放送にも耳を傾けてみてください。
取組の情報
相撲で対戦するお相撲さんの情報は名前だけでは不十分ですよね。
そこで場内放送のアナウンサーがそのお相撲さんの出身地とどこの部屋に所属しているかも教えてくれます。
また、その時の呼出しと行司が誰かという事もアナウンスします。
決まり手の情報
ただ、「こっちが勝った、あっちが負けた」という情報だけではなく、どんな決まり手で勝負が決まったのかということも大切な情報です。
「只今の決まり手は、寄り切り、寄り切って、〇〇の勝ち」といったように、違う言い方で二回言うのが通常です。
ただし、決まり手の種類によっては、言葉の変化のさせ方が異なります。
横綱の土俵入りのアナウンス
相撲の中でも頂点にいる横綱のアナウンスはやはり少し違います。
まず、花道から拍子木の音が聞こえてきたら、「東方より横綱〇〇、土俵入りであります」と言い、横綱と太刀持ちの力士、露払いの力士が溜まりに立ったら、「横綱〇〇、露払い〇〇、太刀持ち〇〇、行司は〇〇であります」と言います。
特別な取組はアナウンスも違うんですね。
このように、相撲の行司の掛け声にはたくさんの種類があり、また「はっけよい」という言葉にもいくつかの語源があるのです。
主役であるお相撲さん以外にも、色んなことに目を向けて勉強してみるのも良いかも知れませんね。













