お葬式などに参列したあとに、塩を使いお清めをすることもありますよね。でも、なぜ塩を使ってお清めをするのかご存知ですか?
塩を使ってお清めをするとどんな効果があるのでしょうか。そもそも塩を使うようになった理由は何?
そこで今回は、お清めに塩を使う理由と、塩を使って行うお清めの方法についてお伝えします。是非チェックしてみてください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

遠方の葬儀に子連れで参列する時の判断基準と子供の服装・マナー
遠方で葬儀が行われるとき、子供を連れて葬儀に参列すること、特に小さい子供を連れて葬儀に参加するのはと...
-

合気道と空手の違い!子供に習わせたい時の判断基準と特徴を解説
子供に武術を習わせたいと思っているお母さんの中には、合気道と空手のどちらを習わせたら良いか迷っている...
-
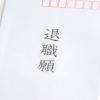
離職票の退職理由が体調不良の場合に手続きや知っておきたいこと
離職票の退職理由が体調不良の場合には、失業給付のことなど手続きを確認しておく必要があります。...
-

香典の金額は2万円でもいいの?夫婦連名で香典を包む時の考え方
香典を夫婦連名でそれぞれ1万円包みたい場合、封筒の中身の金額は2万円になります。ただこの2万円と...
スポンサーリンク
お清めに塩を使うのは一体なぜ?
法事などに参加すると、お清めで塩を使うことがあります。日本の古くからの国技である相撲でも、土俵を清めるために塩を用いますね。
しかしほとんどの人が、なぜお清めに塩を使うのかということを知らない人が多いのではないでしょうか。
今回はお清めに塩を使う理由や、塩を使ったお清めの方法などに付いてまとめてみました。
まずはお清めに塩を使う理由から見ていきましょう。
現代の日本でお清めに塩を使う理由をさかのぼると、日本の神話にたどり着きます。日本最古の歴史書として知られる古事記には、黄泉の国からこの世に帰ったイザナギノミコトが海水で身を清めたとあります。
このことから、穢れは塩によって落とされると考えられてきました。そしてお清めには塩を使うという習慣が日本で生まれました。
お葬式で塩を使ってお清めをする理由についてですが、亡くなった方が穢れだという意味では決してありません。残された私達の生活をきちんと元に戻す、という意味でお葬式では塩でのお清めがされています。
なぜ使うかは身を清めるため・塩を使ったお清めの方法
では、塩を使ったお清めの方法について詳しくご説明したいと思います。
お清めは必ず家に入る前に行います。玄関の敷居を跨いでしまった後では意味がありません。
まずは手を水で洗います。できれば葬儀に参加しなかった人にかけてもらえると良いですが、この手順は省略されることも多いです。
次に塩を身体に振りかけます。振りかける順番は胸→背中→足元の順番です。1箇所に付き1つまみずつ振りかけましょう。これもできれば自分以外の人にやってもらえると良いですね。
三箇所に塩を振りかけたら、服についた塩を軽く払います。
身体に付いた塩を全て地面に落としたら、最後にその塩を足で踏んで完了です。
お清めの塩はお清めの塩として作られたものなので、調味料などで料理に使うことはできません。もったいないと感じても、捨ててしまうようにしましょう。
盛り塩でお清めできるのはなぜ?邪気払いの方法
一般家庭の玄関先や、飲食店の玄関先などでたまに盛り塩を見かけます。盛り塩には邪気払いの効果があるとされています。また、盛り塩の使い方によっては結界を貼ることもできるのだとか。意外と私達の身近にある盛り塩について、少しだけご説明いたしましょう。
盛り塩に使う塩は粗塩です。適当な大きさの小皿に粗塩を三角錐の形に整えます。玄関などの人の出入りの多い場所に置けば、邪気払いとしての盛り塩の完成です。
日常の様々な不調や不幸は邪気によるものもあると考えられており、そうしたものを追い払ってくれるのが盛り塩です。邪気を払い、家族やお店を守るために盛り塩をするのですね。
盛り塩で結界を張ることもできます。結界とは、邪気を追い出した綺麗な空間を作るということです。部屋の四隅に盛り塩を置けば、それだけで結界の完成です。
塩は昔からとても貴重なものだと考えられてきました。神道という日本の宗教では、神棚に毎日塩をあげます。そのような神聖な成分であると考えられているからこそ、盛り塩は邪気を払うと考えられているのですね。
こんな方法でもお清めすることができます
お清めをする方法は他にも色々あります。少し疲れてきたな、と感じたときや、嫌な感じがするときに気分転換の1つとしてもいかがでしょうか。
お清めの色々な方法
- 煎り塩で掃除をしましょう
フライパンで塩を煎り、水分を飛ばします。部屋の窓を開けて新しい空気を入れながら、心をこめて丁寧に掃除をします。最後に煎った塩を部屋に撒いて掃除機で吸い取ります。 - 日光浴をしましょう
日光浴は1番簡単なお清めの方法かもしれません。昔から、陰の気は太陽の光で浄化されると考えられてきました。 - 神聖な場所に行きましょう
神社やパワースポットなど、神聖な場所に行くだけでもお清めされます。神聖な場所で大きく呼吸をすれば身体から邪気を追い出し、神聖な空気を取り込むことができます。
お清めの塩が必要かどうかはその人の考え方次第
なぜお清めに塩が使われるかはこれで理解いただけたかと思います。しかし邪気を払うために絶対に塩でお清めをするべき、ということではありません。
現代の日本の葬儀は文化の変化や時代の流れよって、これまでさまざまな形に変化してきました。これからも少しずつですが変化していくでしょう。
もともと最初に行われていたままの葬儀の形を残している宗教はないといっても過言ではありません。例えば、祭壇や位牌、年忌法要などの習慣は儒教の影響を受けています。戒名や火葬などの習慣は仏教の影響ですし、葬儀の際に黒い喪服を着る習慣は西洋からの文化の影響を受けたものです。
絶対にこうしなくてはいけないという決まりは無いといって良いでしょう。このうように時代と共に変化する葬儀のしきたりの中で、大切なのは自分がどうしたいかということではないでしょうか。
塩によるお清めをやるもやらないも個人の自由です。自分の価値観で、したいと思えばすれば良いのです。それを誰かに押し付けられる理由もありませんし、誰かに押し付けるようなことがあってもいけません。なぜお清めに塩が使われるかはこれで理解いただけたかと思います。しかし邪気を払うために絶対に塩でお清めをするべき、ということではありません。















